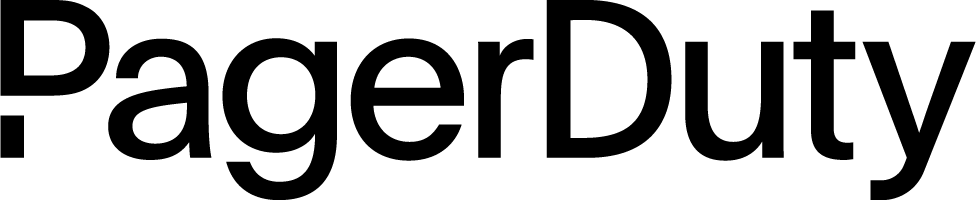The Blameless Postmortem
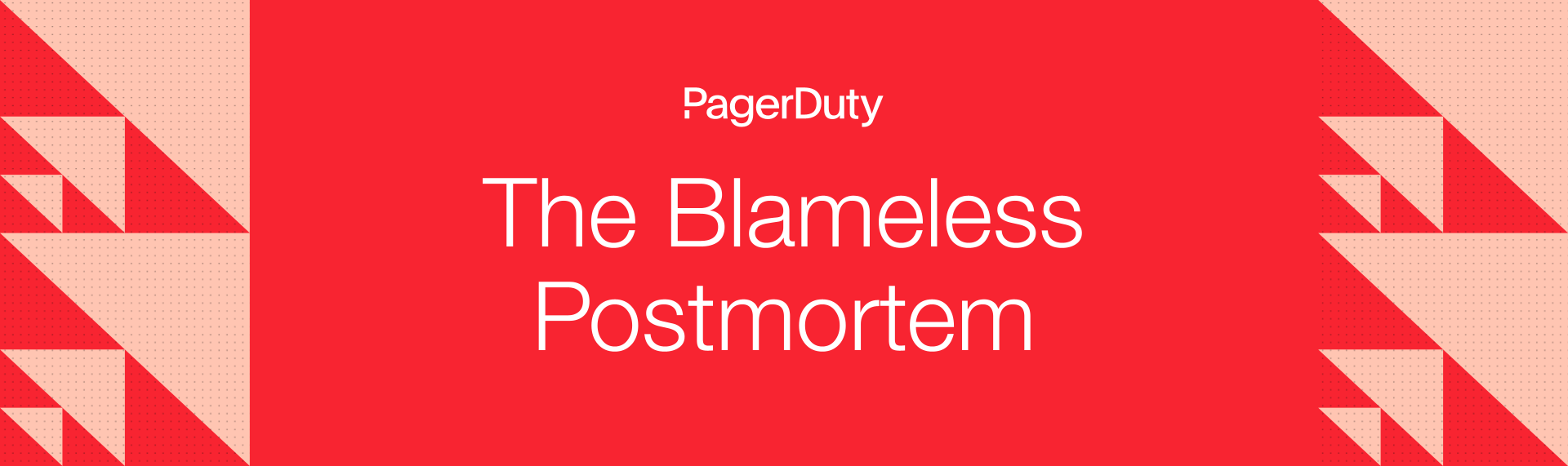
情報技術のプロフェッショナルとして、私たちは複雑なシステムでは障害が避けられないことを理解しています。重要なのは、障害が発生した時にどう対応するかです。 The Field Guide to Understanding Human Error の中で、Sidney Dekkerはヒューマンエラーに関する2つの見方を説明しています:1)古い見方では、人々のミスが障害の原因であるとし、2)新しい見方では、ヒューマンエラーをシステム的な問題の症状として扱います。古い見方では「腐ったリンゴ理論」のように、望ましくない行いをする人を取り除けば障害を防げると信じられています。この見方は個人の性格を彼らの行動に結びつけ、過失や悪意がエラーにつながると想定しているのです。
ヒューマンエラーに関する古い見方に従う組織では、不注意によってインシデントを引き起こした個人が叱責されることがあります。このように非難を行い罰することへの衝動は、将来の障害を防ぐ上で必要な知識共有を妨げるという予期せぬ影響をもたらします。 エンジニアは非難されることを恐れて、インシデントが発生した際に発言することをためらうでしょう。この沈黙はインシデントの平均確認時間(MTTA)、平均解決時間(MTTR)を増加させ、インシデントの影響を悪化させます。
ポストモーテムプロセスを学習とシステム改善につなげるためには、ヒューマンエラーに関する新しい見方に従う必要があります。ソフトウェア開発における複雑なシステムでは、様々な条件が相互作用して障害を引き起こします。ポストモーテムの目的は、インシデントの発生につながったシステム的要因を理解し、この種の障害が再発するのを防ぐためのアクションを特定することです。 ブレームレス(非難のない)なポストモーテムは、「誰が」ミスを犯したかではなく、「どのように」ミスが発生したかに焦点を当てます。これは、多くの先進的な組織(例えばブレームレスなポストモーテムのパイオニアであるEtsy)が活用している重要なマインドセットであり、罰に対する恐怖を排除することにより、実際に何が起こったかをエンジニアが真の意味で客観的な説明をできるようにし、ポストモーテムが適切なトーンで行われることを保証します。
なぜブレーム(非難)を意識することが難しいのか#
継続的改善の文化を望むことは簡単ですが、学習に求められる非難のない状態の実践は難しいです。予期せぬことが発生する障害の性質は、自ずと人間が理解する妨げとなるような反応を招きます。情報を処理する際に、人間の心は無意識のうちにショートカットを取ります。一般的な経験則を適用することで、心は正確さよりもタイムリーさに最適化されるのです。これが誤った結論を生み出す場合、それは認知バイアスと呼ばれます。
J. Paul Reedは、非難する傾向が何百万年もの進化的神経生物学によって配線されているため、ブレームレスなポストモーテムは神話だと主張しています。この傾向を無視したり、完全に排除しようとしたりすることは不可能です。「ブレームアウェア(非難を意識する)」であることの方が生産的です。私たちのバイアスを意識することで、それらが発生した時に識別し、乗り越える取り組みを行えるでしょう。 以下ではいくつかのバイアスについて触れますが、詳細については、ポストモーテムを実施する際に意識すべき認知バイアスについてのLindsay Holmwoodの記事をお読みください。
基本的帰属エラー(fundamental attribution error)は、人々の行動が、彼らの状況ではなく性格を反映したものであると信じる傾向です。これはヒューマンエラーの古い見方を表し、障害を不注意で無能な悪い人物のせいにします。皮肉なことに、私たちは自分自身の行動を説明する際には、自分の性格ではなく状況によって説明する傾向があります。このように他者を非難する傾向と戦うには、個人が取った具体的な行動ではなく、状況的な原因へ意図的に分析の焦点を当てることです。
もう一つの広く見られる認知バイアスは確証バイアス(confirmation bias)で、これは既存の信念を強化する情報を好む傾向です。曖昧な情報に直面すると、私たちはそれを既存の仮定を支持する方法で解釈する傾向があります。ヒューマンエラーの古い見方と組み合わさると、このバイアスはポストモーテムにとって危険です。なぜなら、それは腐ったリンゴを非難しようとする流れにつながるからです。個人に責任があるという仮定でアプローチすると、反対の証拠があるにもかかわらず、その信念を支持する方法を探してしまうでしょう。
確証バイアスと戦うために、調査の過程で逆の立場をとる代弁者を任命することをHolmwoodは提案しています。ただし、逆の立場をとる代弁者によって否定性や対立性がもたされることには注意してください。また、他のチームから誰かを招いて、彼らの心に浮かぶあらゆる質問をしてもらうことで、確証バイアスに対抗することもできます。これにより、チームが当然と考えるようになっていた調査の方向性が明らかになります。
後知恵バイアス(hindsight bias)は、判断を形作るために事象を思い出す際の記憶の歪みの一種です。結果を知っていると、当時はそれを予測する客観的な根拠がほとんどまたは全くなかったにもかかわらず、その事象が容易に予測可能だったと見なしてしまいがちです。私たちはしばしば、自分自身をよりよく見せるようなやりかたで出来事を思い出します。例えば、インシデントの原因を分析している人が、それが起こるとを予期していたと信じる場合が挙げられます。このバイアスを体現すると、チーム内の防御と分裂を招きかねません。Holmwoodは、後知恵バイアスを避けるために、事象を予見の観点から説明することを提案しています。すなわちタイムライン分析をインシデント発生前の時点から始め、解決から逆算するのではなく、前に進むようにするのです。
注意すべきもう一つの一般的なバイアスは否定性バイアス(negativity bias)です。これは、否定的な性質のもののほうが、中立的または肯定的な性質のものよりも、人の精神状態に大きな影響を与えるという概念です。社会的判断に関する研究では、他者に対する印象において、否定的な情報がとてつもなく大きな影響を与えることが示されています。これは「腐ったリンゴ理論」、つまり組織内に障害の責任を負うべき好ましくない人物がいるという信念に関連しています。研究はまた、人々が否定的な結果を他の人の意図によるものだとする可能性が、中立的および肯定的な結果よりも高いことを示しています。これもまた、重大なインシデントを説明するために個人の性格を非難する傾向を説明しています。
実際には、物事がうまくいくことの方が、うまくいかないことよりも多いのですが、私たちは否定的な出来事に焦点を当て、その重要性を強調する傾向があります。インシデントを否定的な出来事として焦点を当て、誇張し、内面化することは、士気を低下させ、燃え尽き症候群を招く可能性があります。インシデントを学習の機会として再構築し、対応でうまく対処された事柄を説明することを忘れないようにすることで、視点のバランスを取っていきましょう。
認知バイアス#
| バイアス | 定義 | 対策 |
|---|---|---|
| 基本的帰属エラー | 人々の行動には彼らの状況ではなく性格が反映されているものとみなす。 | |
| 確証バイアス | 既存の立場を強化する情報を好む。 | 調査の過程で逆の立場の代弁者を任命する。 |
| 後知恵バイアス | 結果を知っているため、それを予測する客観的な根拠がほとんどまたは全くなかったにもかかわらず、インシデントが避けられなかったとみなす。 | 事象を予見の観点から説明する。タイムライン分析をインシデントの前の時点から始め、解決から逆算するのではなく、前に進む。 |
| 否定性バイアス | より否定的な性質のものが、中立的または肯定的なものよりも、人の精神状態に大きな影響を与える。 | インシデントを学習の機会として再構築し、インシデント対応でうまく処理されたことを説明することを忘れないようにする。 |
私たち全員がこれらの認知バイアスを持っていて、見過ごされると事象の歪んだ見方につながったり、チームの関係を損なったりする可能性があります。これらの傾向を意識することで、バイアスが発生した時に認識することが重要です。ポストモーテムを共同プロセスにすることで、チームはグループとして非難を特定し、分析をより深く掘り下げることができます。
ブレームレス(または非難を意識した)文化をどのように育むか#
非難を認識し、それを乗り越えることは、言うは易く行うは難しです。ブレームレスな文化に向けてどのような行動をとればよいでしょうか?Holmwoodは、非難を最小限に抑え、学習を最大化するために使用する言葉の重要性について雄弁に書いています。彼は「何」という質問(例えば、「何が起きていると思いましたか?」「次に何をしましたか?」)をするよう促しています。「何」という質問をすることで、インシデントに寄与した大きな要因に分析の基礎を置きます。
彼の記事「The Infinite Hows」の中で、John Allspawは「どのように」という質問をするよう勧めています。なぜなら、それらは人々に出来事が起こることを可能にした条件(少なくともいくつか)を説明させるからです。Holmwoodもまた、「どのように」という質問が技術的な詳細を明確にし、人々を彼らが取った行動から距離を置かせるのに役立つと指摘しています。「なぜ」という質問は避けてください。なぜなら、それは人々に自分の行動を正当化させ、非難を帰することになるからです。
Crucial Accountabilityでは、期待と現実の不一致に関する難しい会話にアプローチするのに役立つフレームワークが提供されており、感情が高まるようなポストモーテムにも適用できます。障害を分析する際、私たちは感情を駆り立て、最悪の行動を正当化しようとする被害者、悪役、無力な物語に陥る可能性があります。物語の残りの部分を語ることで、非難を乗り越えることができます。問題における、あなた自身と他者の役割を考慮してください。合理的で理性的で良識のある人が、インシデントの原因となったように見える行動を取った理由を自問してください。この思考は、インシデントにつながった複数のシステム的要因に注意を向けるのに役立ちます。
最善の努力をしてブレームレスであろうとしても、ポストモーテムミーティング中に誰かが非難されていると感じると、人は防御的になる可能性があります。これが起こった場合、生産的な議論を続けるために互いの目的意識と尊重を回復するよう努めてください。ポストモーテムの目的はインシデントにつながったシステム的要因を理解し、将来の障害を減らすためのアクションを共同で特定することだと再確認することで、相互の目的意識を回復します。しばしば、人々は自分の性格が攻撃されていると感じると防御的に行動します。対比することで相互の尊重を回復します。あなたが意図しなかったこと(「あなたが仕事が下手だと言うつもりはありませんでした」)と、あなたが意図したこと(「任意の対応者がその行動を取るような状況的要因を尋ねるつもりでした」)を対比させてください。非難を暗示する個人の動機からは、調査の焦点を逸らしてください。特定されていない対応者に抽象化することで、システム障害に寄与した可能性のあることについて、他の対応者がより多くの提案を行いやすくなります。
重要なポイント
- 「誰が」「なぜ」ではなく、「何を」「どのように」という質問をする。
- 複数の多様な視点を考慮する。
- 合理的で理性的で良識のある人が特定の行動を取った理由を自問する。
- 人間の行動について尋ねる際、特定されていない対応者に抽象化する。誰でも同じミスを犯す可能性がある。
- あなたが意図しなかったことと意図したことを対比させることで、相互の目的と尊重を回復する。